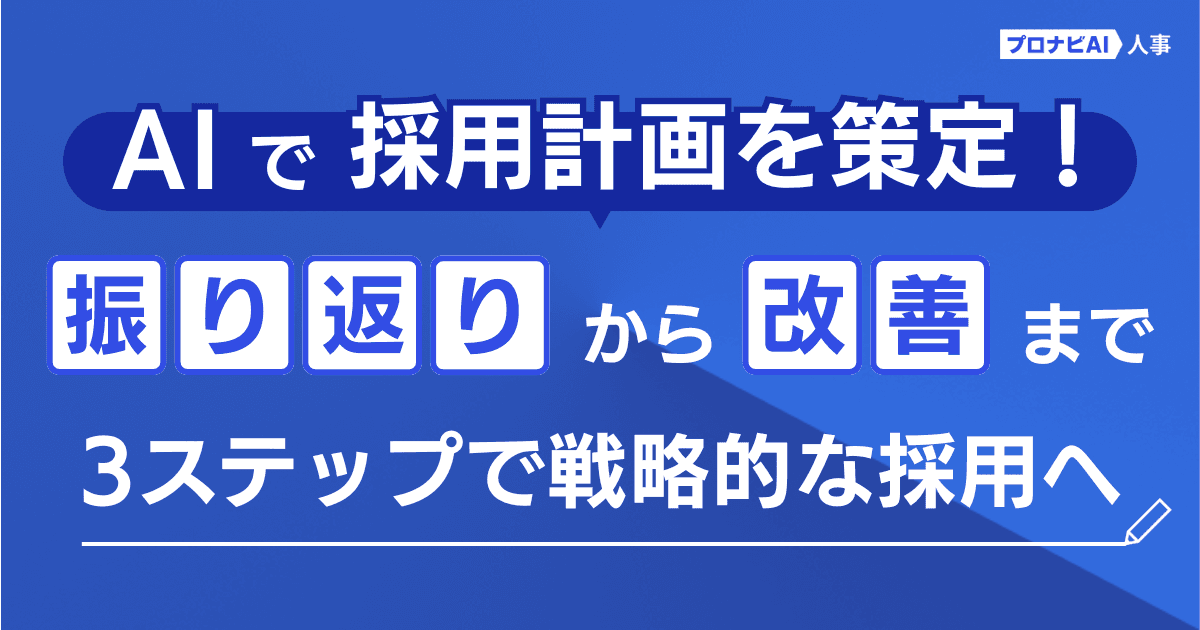【この記事でわかること】
- AI(ChatGPT)を活用して採用計画を策定する具体的な3ステップ
- 明日から使える、コピペOKのプロンプトと実際の出力例
なぜ、従来の採用計画は「大変な割に活かされない」のか?
多くの企業で採用計画の策定は、多大な労力を要するにもかかわらず、その効果を十分に発揮できていないというジレンマを抱えています。その背景には、共通する3つの構造的な課題が存在します。

課題1. 振り返りが「感想」で終わり、具体的な改善策に繋がらない
「今年は良い候補者と多く会えた」「面接のドタキャンが多かった気がする」といった定性的な振り返りは重要ですが、それだけでは具体的なアクションに繋がりません。 感想レベルの共有で終わってしまい、根本原因の特定や、次年度に向けた再現性のある施策の立案まで至らないケースが非常に多いのが実情です。
課題2. データの収集・分析に時間がかかる割に活用されない
各求人媒体からの応募数や選考フェーズごとの通過率、面接官ごとの評価データなど、分析すべきデータは多岐にわたります。これらのデータを手作業でExcelなどに集計・分析するだけで数日を要することも珍しくありません。 さらに、苦労して作成した分析資料も、情報量が多すぎるために関係者に読み込まれず、結果的に意思決定に活かされないという悲しい現実もあります。
課題3. 前年踏襲と勘にたよった計画になりやすい
膨大な作業と時間に追われた結果、客観的なデータ分析に基づく大胆な戦略変更は難しくなります。そのため、「昨年はこの媒体から5名採用できたから、今年も同程度の予算で」といったように、前年の実績と担当者の経験則に頼った、大きな変化のない計画に落ち着きがちです。 これでは、市場の変化や新たな課題に対応することは困難です。
AIが解決!採用計画は「作る」から「育てる」時代へ
これまで手間と時間のかかる作業だった採用計画策定は、AIの登場によって大きく変わりつつあります。AIは、戦略立案をサポートしてくれる、優秀な「分析官」であり「壁打ち相手」としても活用できる存在です。
AIで何が変わる?3つのメリット
ChatGPTのような生成AIを活用することで、採用計画の策定は以下のように変わります。

1. 面倒な定性データの分析を”秒”で終わらせる
これまで見過ごされがちだった、あるいは分析に手間がかかりすぎていた面接官の評価コメントや不採用理由といったテキストデータを、AIは瞬時に読み込み、傾向や重要なポイントを要約・抽出します。これにより、これまで気づかなかった課題や、ハイパフォーマーに共通する資質などを発見できます。
2. 勘や経験頼りから「データに基づく」客観的な意思決定へ
AIは、バイアスのかからない客観的な視点でデータを分析します。「どの選考フェーズで、どのような理由での辞退が最も多いのか」「合格者と不合格者では、評価コメントにどのような違いがあるのか」といった問いに対し、明確なデータに基づいた答えを提示してくれます。
3. 計画策定の時間を削減し、重要な業務に集中できる
実際に当社の採用チームでも、この記事で紹介する手法を導入し、計画策定に関わる工数を約60%削減できました。 AIにデータ分析や資料のドラフト作成を任せることで、人事担当者は、候補者一人ひとりとのコミュニケーションや、経営層との人材戦略のすり合わせといった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
【3ステップで実践】ChatGPTで次年度採用計画を策定する具体的な方法
ここからは、実際にChatGPTを使って次年度採用計画を策定するための具体的な手順を、3つのステップに分けて解説します。紹介するプロンプトはコピー&ペーストして、自社の状況に合わせて[ ]の中身を書き換えるだけで使えます。

ステップ1. AIで今年の採用活動を「高速で」振り返る
まずは、今年の採用活動で蓄積された「生きたデータ」をAIに分析させ、客観的な事実を把握することから始めます。特に価値が高いのが、面接官が残した評価コメントです。
- やること: 今年度の採用面接における「合格者」と「不合格者」それぞれの評価コメントをテキストデータとして用意し、AIにそれぞれの特徴を分析・要約させる
【コピペOK】候補者の特徴を分析するプロンプト
# 命令書 あなたは優秀な採用アナリストです。 以下の#制約条件と#入力データに基づいて、採用候補者の特徴を分析してください。 # 制約条件 ・合格者と不合格者、それぞれの評価コメントから、頻出するキーワードや評価ポイントを特定してください。 ・両者の特徴を比較し、採用要件との整合性や、評価基準のブレがないか考察してください。 ・分析結果は、箇条書きで分かりやすくまとめてください。 # 入力データ ・採用ポジション:[営業職] ・合格者の評価コメント:[ここに合格者全員の評価コメントを貼り付ける。例:「論理的思考力が高く、顧客の課題を的確に捉えられそう」「目標達成意欲が非常に強く、粘り強さを感じる」...] ・不合格者の評価コメント:[ここに不合格者全員の評価コメントを貼り付ける。例:「自己PRが抽象的で、強みが分かりにくい」「チームでの協業経験について具体的に話せていなかった」...]
ステップ2. AIを壁打ち相手に「真の課題」を深掘りする
ステップ1で得られた客観的な分析結果をもとに、AIと対話しながら課題の根本原因を探ります。AIは優れた壁打ち相手となり、多角的な視点を提供してくれます。
- やること: ステップ1の分析結果をAIに提示し、課題の根本原因と改善策のアイデア出しを依頼する
【コピペOK】課題の根本原因を探るプロンプト
この分析結果(特に考察部分)を踏まえて、以下の点について壁打ち相手としてディスカッションしてください。 # 議論したいテーマ 1. 「主体性」の定義が面接官によってブレてしまう根本的な原因は何だと考えられますか?考えられる可能性を3つ挙げてください。 2. この「評価基準のブレ」という課題を解決するために、明日から着手できる具体的なアクションプランを5つ提案してください。 3. その他、この分析結果から読み取れる、次年度の採用活動における隠れた課題や改善のチャンスがあれば教えてください。
この対話を通じて、「面接官トレーニングの内容が不十分だったのではないか」「評価シートの項目が曖昧だったのではないか」といった具体的な仮説や、「評価項目定義ワークショップの開催」「キャリブレーション(評価基準のすり合わせ)会議の定例化」といった具体的な解決策のアイデアを得ることができます。
ステップ3. AIと一緒に「次年度採用計画書」の骨子を作る
最後にこれまでの分析と議論の結果を統合し、AIに「次年度採用計画書」のドラフトを作成させます。これにより、資料作成の時間を大幅に短縮できます。
- やること:ステップ1・2で得られた情報をインプットとして、計画書の骨子(目次と各項目の概要)を作成させる
【コピペOK】採用計画書の骨子を作成するプロンプト
# 命令書 あなたは戦略人事のプロフェッショナルです。 これまでの一連の分析結果と議論を踏まえて、経営層に提出するための「[202X年度 営業職]採用計画書」の骨子を作成してください。 # 含めるべき要素 ・現状の課題(ステップ1, 2の分析結果を要約) ・次年度の採用目標(KGI/KPI) ・ターゲットとなる人材像(ペルソナ)の再定義 ・具体的なアクションプラン(選考プロセスの見直し、面接官トレーニングの強化など) ・スケジュール ・予算 # アウトプット形式 ・マークダウン形式で、見出しを活用して構造的に記述してください。
AIは、これまでの情報を整理し、構造化された計画書のドラフトを生成します。この骨子をベースに、具体的な数値目標や詳細な表現を追記・修正するだけで、質の高い計画書を短時間で完成させることができます。
AI活用の難しさを乗り越えるためのヒント
「AIは便利そうだけど、何だか難しそう…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、心配は不要です。今日から始めるための簡単なヒントと、注意点をお伝えします。
まずは無料版ChatGPTでOK!今日から始められる
この記事で紹介したプロンプトは、多くの場合、無料版のChatGPT(GPT-3.5)でも十分に機能します。特別なツールや契約は不要で、アカウントを登録するだけですぐに試すことができます。
完璧を目指さない!「コピペして、少し変える」から始めよう
最初から完璧なプロンプトを作ろうとする必要はありません。まずは、この記事のプロンプトをコピー&ペーストし、[ ]の中身を自社の状況に合わせて書き換えることから始めてみてください。「AIにこんなことを聞いてもいいんだ」という感覚を掴むことが、活用の第一歩です。
機密情報の扱いはどうする?注意点と対策
AIを利用する上で最も重要なのが、情報セキュリティです。 個人情報(氏名、連絡先など)や企業の機密情報を、そのまま入力することは絶対に避けてください。
対策1. 情報を匿名化・抽象化する
候補者の氏名や具体的なプロジェクト名などは削除・抽象化してから入力しましょう。
対策2. オプトアウト設定(有料版など)
ChatGPTの有料版などでは、入力したデータをAIの学習に利用させない「オプトアウト設定」が可能です。機密性の高い情報を扱う可能性がある場合は、これらの設定を必ず確認・利用してください。
対策3:API経由での利用
セキュリティをさらに重視する場合は、API(Application Programming Interface)経由で利用する方法があります。API経由のデータは、原則としてAIの学習には利用されません。
AIを使いこなし、戦略人事へシフトさせる
AIの活用は、単なる業務効率化に留まりません。人事担当者の役割そのものを進化させる可能性を秘めています。
取り組むべき、付加価値の高い仕事データ分析や資料作成といった作業をAIに任せることで、人事担当者は時間という最も貴重な資源を手に入れることができます。その時間を使って、以下のような人でなければできない本質的な業務に注力すべきです。
- 候補者体験(Candidate Experience)の向上
- 社員紹介(リファラル)制度の活性化
- 経営陣との人材戦略に関する対話
- 入社後活躍を見据えたオンボーディングの設計
AIが「頼れる相棒」になる
AIは、人事の仕事を奪う脅威ではありません。むしろ、面倒で時間のかかる作業から私たちを解放し、より創造的で戦略的な仕事に集中させてくれる「頼れる相棒」です。 AIを使いこなすことが、これからの時代の人事担当者にとって必須のスキルとなるでしょう。
まとめ:AIで採用計画の常識を変え、最高のチーム作りを始めよう
これまで多くの人事担当者を悩ませてきた「次年度採用計画」の策定は、AIを活用することで、「時間がかかる大変な作業」から