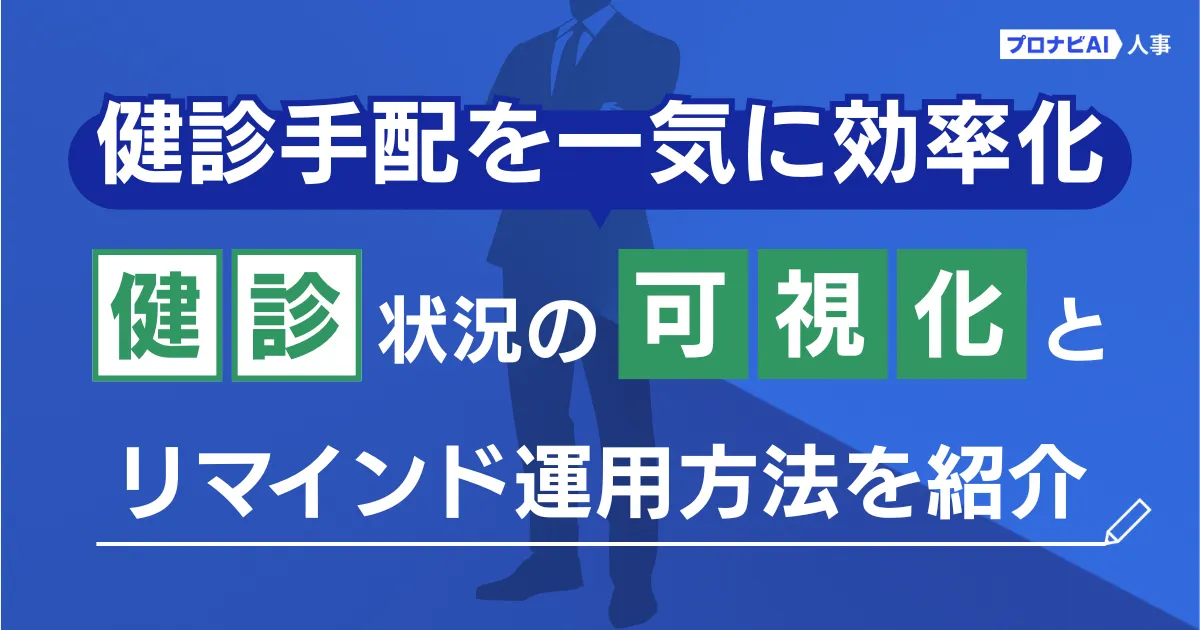【この記事でわかること】
- 案内メール作成や未受診者への催促をAIで自動化する3つのハック
- 今すぐ使える、コピペOKの「健康診断AI活用プロンプト」集
健康診断の手配、正直「面倒」ではありませんか?
従業員一人ひとりの健康を守る、法で定められた重要な義務。その意義は重々承知しているものの、健康診断手配に、毎年多くの時間が奪われているのではないでしょうか。
- コア業務の合間を縫って、膨大な調整業務に対応している
- 案内文の些細な言い回しに悩み、作成に1時間以上かかってしまう
- 受診状況をExcelで管理しているが、更新漏れや確認ミスが怖い
- 未受診者への催促メールを送るのが、精神的に少し負担に感じる
このような定型業務から解放され、もっと戦略的な人事業務に集中したい。本記事は、そう願うすべての担当者の皆様に向けた、AIによる改善方法を紹介します。
健康診断の手配、なぜこんなに大変?5つの面倒ポイントを再確認
まずは、人事担当者が毎年直面している課題を言語化し、整理してみましょう。健康診断の手配業務には、主に5つの「面倒なポイント」が潜んでいます。

1. 医療機関の選定と予約調整
従業員の居住地や勤務形態(リモートワークなど)を考慮し、複数の医療機関を選定。団体予約の調整や、個別受診のルール策定など、外部との煩雑なコミュニケーションが発生します。
2. 全従業員への案内メール
丁寧かつ分かりやすい案内文の作成は、意外と神経を使います。対象者や受診コースごとに内容を微調整する必要もあり、送信リストの管理も手間がかかります。
3. 予約状況のリアルタイム把握とリマインド
「誰が予約して、誰がまだなのか」を正確に把握するのは一苦労です。特にExcelなど手動での管理は、入力ミスや更新漏れのリスクと常に隣り合わせです。
4. 未受診者への根気強い催促
受診期限が迫る中、未受診者へ個別で催促するのは骨が折れる作業です。相手を不快にさせないよう配慮しつつ、会社の義務であることを伝えなければなりません。
5. 費用処理と実施結果の報告
医療機関への支払い処理や、従業員からの立替経費の精算、そして産業医への報告や労働基準監督署への報告書作成など、事後処理も多岐にわたります。
これらの業務の一つひとつは小さく見えても、積み重なることで担当者の貴重な時間を大きく削っているのです。
健康診断手配の標準フローと注意点
AI活用に進む前に、まずは基本となる標準フローと法的な注意点をおさらいしましょう。この基礎を理解しておくことで、どの部分をAIで効率化できるかが明確になります。

Step1. 実施計画の策定
- 実施時期の決定:年間の業務計画に沿って決定する
- 対象者のリストアップ:常時使用する労働者が対象。パート・アルバイトも労働時間によっては対象となる
- 健診コースの決定:法定の必須項目に加え、年齢や性別に応じたオプション検査(人間ドックなど)の補助範囲を決定する
Step2. 医療機関の選定・契約
- 健診コースや費用、立地などを比較検討し、委託する医療機関を決定・契約する
Step3. 従業員への案内・予約受付
- 全従業員に向け、健診の目的や受診方法、予約締切などを明記した案内を送付する
- 医療機関への予約を従業員自身が行うか、会社で一括して行うかをルール化し、予約受付を開始する
Step4. 受診状況の確認・リマインド
- 予約状況や受診状況を定期的に確認し、未予約・未受診の従業員へリマインドを行う
Step5. 費用精算・結果管理と事後措置
- 医療機関への支払いや、従業員の立替経費を精算する
- 健診結果を回収・保管し、有所見者に対しては産業医や保健師による事後措置(就業上の措置の検討など)を行う
- 労働基準監督署へ「定期健康診断結果報告書」を提出する(常時50人以上の労働者を使用する場合)
【法的ポイント】これだけは押さえたい!安全配慮義務とは
会社には、労働契約法第5条に基づき「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)」が課せられています。健康診断の実施は、この義務を果たすための重要な取り組みの一つです。単なる「作業」ではなく、従業員の安全と健康を守るための根幹的な責務であることを、改めて認識しておきましょう。
【本題】AIで自動化!健康診断業務が楽になる3つのAIハック
前述した「面倒なポイント」のうち、特に時間と心理的コストがかかるコミュニケーション業務を、AIを使って効率化する具体的な方法を3つご紹介します。
1. 案内メール作成を“1分”で終わらせる
毎年ゼロから作成したり、過去のメールを探し出して修正したりしていませんか? AIを使えば、必要な情報を伝えるだけで、丁寧で分かりやすい案内メールのドラフトが数秒で完成します。
2. 未受診者への催促メールを“状況別”に自動生成
催促メールは、送る相手やタイミングによって文面のトーンを変える必要があります。AIに状況を伝えることで、丁寧なリマインドから、少し強めに依頼する最終催促まで、複数のパターンを瞬時に作成できます。
3. よくある質問への“自動応答チャットボット”を作る
「費用はどこまで会社負担?」「パスワードを忘れました」といった頻出の質問に、その都度対応するのは非効率です。AIに想定問答集(FAQ)を作成させ、それを元に簡易的なチャットボットを用意することで、問い合わせ対応を自動化できます。
今すぐ試せる!コピペOKの「健康診断AI活用プロンプト」集
「AIハックと言われても、具体的にどうすれば…」と感じた方も心配いりません。ここでは、ChatGPTなどの生成AIにコピー&ペーストするだけで、すぐに使える「プロンプト(指示文)」の具体例をご紹介します。
これらのプロンプトは、私たち『プロナビAI人事』編集部で実際に動作検証済みです。
プロンプト1. 丁寧かつ分かりやすい「案内メール」作成
以下のプロンプトの[ ]内をあなたの会社の情報に書き換えて、AIに指示してみてください。驚くほど質の高いドラフトが完成します。
# 命令書
あなたは、SaaS企業の人事部担当者です。以下の制約条件と入力情報をもとに、従業員向けの健康診断の案内メールを作成してください。
# 制約条件
・件名は【重要】で始め、内容が簡潔にわかるようにする。
・丁寧で分かりやすい言葉遣いを徹底する。
・従業員が何をすべきかが明確にわかるよう、箇条書きや番号付きリストを効果的に使用する。
・多忙な従業員にも配慮し、簡潔にまとめる。
# 入力情報
・会社名:株式会社プロナビ
・件名:2024年度 定期健康診断のご案内
・目的:労働安全衛生法に基づく法定健診であり、全従業員の健康維持のため。
・対象者:全正社員、および週30時間以上勤務の契約社員・アルバイト
・受診期間:[2024年8月1日~2024年9月30日]
・予約方法:各自で提携医療機関リストから選択し、直接電話またはWebで予約。予約時に「株式会社プロナビの健康診断」と伝えること。
・費用:法定項目は全額会社負担。オプションの人間ドックは差額の半額(上限2万円)を補助。
・予約締切:[2024年8月31日]
・注意事項:
- 受診当日は保険証を必ず持参すること。
- 予約の変更・キャンセルは前日までに自身で医療機関へ連絡すること。
- 期間内に受診が困難な場合は、人事部の[あなたの名前]まで要相談。
・添付資料:提携医療機関リスト、よくある質問(FAQ)プロンプト2. 未受診者も動かす「催促メール」3パターン
未受診者への催促は、タイミングが重要です。以下のプロンプトは、丁寧なリマインドから最終勧告まで、3つの異なるトーンのメール案を一度に生成するようAIに依頼するものです。
# 命令書 あなたは、人事部の担当者として、健康診断が未受診の従業員に対して催促メールを作成します。以下の制約条件と入力情報に基づき、トーンの異なる3パターンのメール文案を出力してください。 # 制約条件 ・会社の義務であり、従業員本人のための重要な検査であることを伝える。 ・高圧的な表現は避けつつ、受診を促す構成にする。 ・各パターンの違いが明確になるように作成する。 # 入力情報 ・受診締切日:[2024年9月30日] ・現在の状況:締切まであと2週間だが、まだ予約が確認できていない。 ・パターン1のトーン:丁寧なリマインダー。「お忘れではないですか?」というスタンスで、あくまで確認を促す。 ・パターン2のトーン:少し強めの依頼。「締切が迫っておりますので、至急ご予約を」というスタンスで、行動を具体的に促す。 ・パターン3のトーン:最終催促。「法的義務であり、未受診の場合は安全配慮義務の観点から問題となる可能性がある」という事実を伝え、強い対応を求める。
プロンプト3. ChatGPTで“よくある質問”に答えるFAQを作る
頻出質問に自動で回答できるように環境を整えます。以下のプロンプトで、先回りしてFAQを作成し、社内イントラネットなどに掲載しておきましょう。
# 命令書 あなたは、人事のプロフェッショナルです。従業員向けの健康診断に関して、よくある質問とその回答をまとめたFAQリストを作成してください。以下の制約条件と想定される質問項目を参考に、分かりやすく網羅的なリストを出力してください。 # 制約条件 ・質問(Q)と回答(A)の形式で出力する。 ・専門用語を避け、誰にでも理解できる平易な言葉で解説する。 ・回答は具体的で、従業員が次にとるべきアクションがわかるように記述する。 # 想定される質問項目 ・費用負担の範囲について ・提携外の医療機関で受診したい場合の手続き ・受診日当日に体調不良になった場合の対応 ・健診結果は会社に見られるのか? ・再検査(要精密検査)の指示があった場合の対応 ・扶養している家族も受診できるか? ・予約方法がわからない
AI活用で生まれる時間で、「本来やるべき仕事」に集中できる
AIを使って定型業務を効率化する目的は、単に「楽をすること」ではありません。その真の価値は、創出された時間と心の余裕を、より戦略的で付加価値の高い業務に再投資できることにあります。
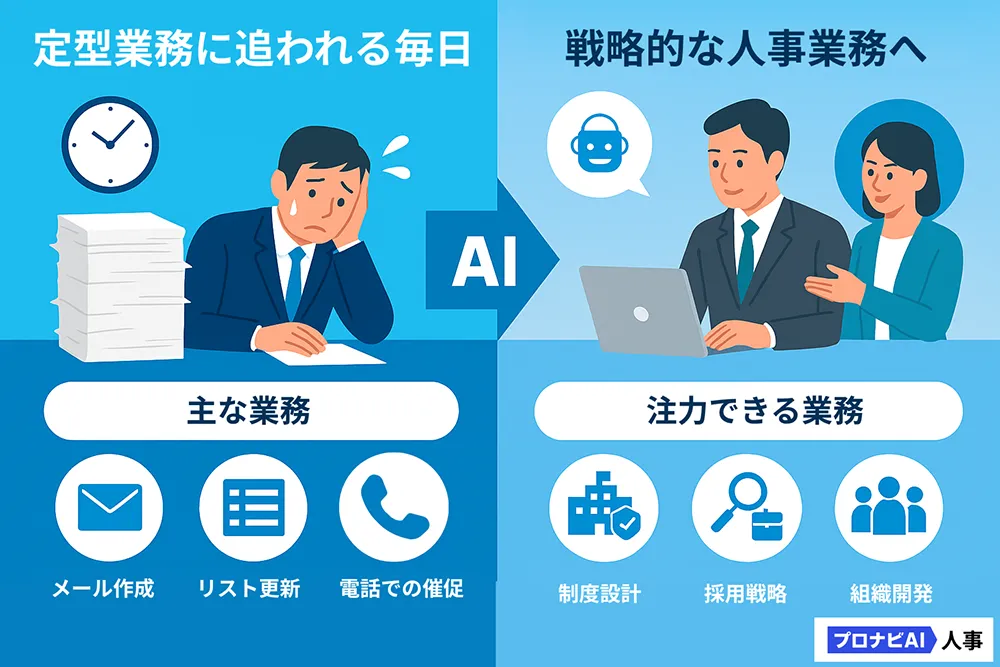
定型業務から解放され、戦略的な業務へシフト
空いた時間で、新しい人事評価制度の設計や、エンゲージメント向上のための施策、未来を担う人材の採用戦略立案など、これまで後回しになりがちだった「会社の未来を創る仕事」に集中できます。
チーム初の「AI業務改善」成功事例に
あなたがこの小さな成功体験をチームや社内に共有することで、他のメンバーや部署にもAI活用の輪が広がるかもしれません。それは、組織全体の生産性向上に繋がる大きな一歩となります。
AIを使いこなす、市場価値の高い人事へ
AIを「脅威」ではなく「有能なアシスタント」として使いこなすスキルは、これからの時代の人事プロフェッショナルにとって必須の能力です。身近な業務からAI活用を始めることは、あなた自身の市場価値を高める自己投資でもあるのです。
まとめ
毎年恒例の健康診断の手配は、その定型性・反復性の高さから、AI活用の効果を最も実感しやすい業務の一つといえます。大掛かりなシステム導入は不要なため、まずは本記事でご紹介したプロンプトをコピー&ペーストして、時短効果を体感してみてください。
その小さな成功体験は、「AIって、意外と使えるじゃないか」という自信に繋がり、人事担当者の働き方を、ひいては組織の働き方を大きく変える原動力となるはずです。